「すもうにかった びんぼうがみ 」
(松谷みよ子 再話、斎藤真成 画、福音館書店 こどものとも1973年1月号、1973.1.1初版発行)
すもうにかった びんぼうがみ|福音館書店 (fukuinkan.co.jp)
大晦日の民話。
貧しくても心優しい働き者の若夫婦が、
我が家の貧乏神に御馳走を食べさせ、
やってくる福の神との相撲勝負を応援すると?
古来より日本の相撲神事は
新年と七夕とに奉納された。
民話にも
「大晦日から新年への年越しの夜の相撲」
が物語られており、
災い転じて福となす大らかな展開が楽しい。
貧しさから豊かさへ、
闇から光への逆転劇は、
冬から春への季節に応じ
穀物を育んできた農民たちの知恵に
深く根差しているのだろう。
( 2023.12.31 Twitter より )
星空の恵みを地におろす – レモン水 (ginmuru-meru.com)
相撲、伎楽、鷺舞、七夕 – レモン水 (ginmuru-meru.com)
水の器と蛇(Bing Image Creator)

Bing Image Creator の表現で、
蛇に似た装飾のある器が宙に浮き、
少女の手に水を注いでいる。
(羽と編んだ髪の位置関係の不自然さ
など目につく部分はあるけれども)
偶然に出来た画像の
「水の器と蛇」との結びつきの
不思議さに惹かれた。
縄文土器と蛇(カガ)については、
以前に考えてみたことがある……
はちみつみかん カガセオ幻想(1)ginmuru-meru
>たとえば縄文土器は、
ナワ状の粘土を
ぐるぐる積み上げるよう重ねて、
ツボ型の器にしたりする。
カガが、蛇や籠を表す言葉だとして、
カガルって言葉は縁取る意味だとして、
カガリビが暗闇のなかで
周囲の輪郭をふちどらせる
炎の意味だとしたら、
すっきりイメージがまとまる。
縄文土器をつくる人の目線で。
( 2023.6.4 Twitter より )
( 2023.5.31 イラスト作成 Bing Image Creator )
四月愚者
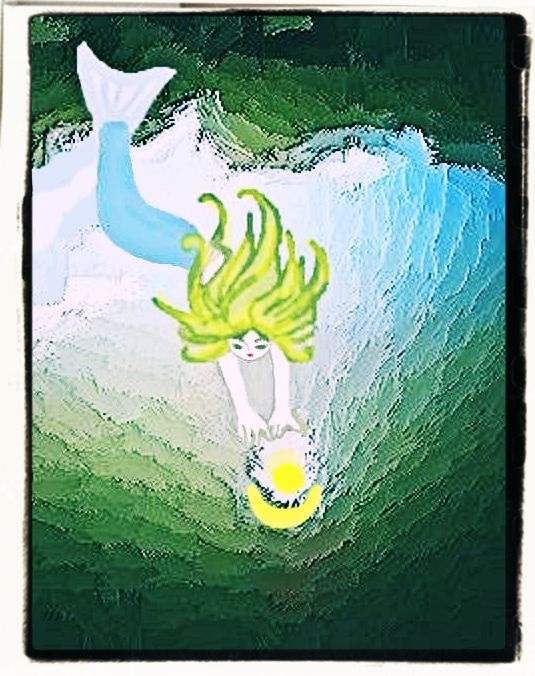
古代人の死生観、洋の東西をざっくり越えて、
前世、お魚や鳥さんや馬や牛や羊や豚だったの。
この世を去ったら、舟で星の海に出て、
天の川の星粒になって空から見守り、
雨といっしょに地上に降りて
穀物に宿って実るから。
達者で暮らしてね。
こんな感じだったかも?
と家族に話し、沈黙された。
エイプリルフールの午前。
絵本の読み聞かせ調で語ってみたのである……
(淡々と真顔で)
(ゆえに、たぶん反応に困ったのだと思う)
(新年度の始まり、私は
道化と犠牲王と鬼について等を検索し、
見つけたPDFを読んだのだが、
7年前にも同じその論考をダウンロード
していたことに気づいた……)

この一年こそは
滝に打たれるなり
手堅い読書に励むなり
精進しようと思ふ
四月愚者。
(その決意はゆるい……)
Orz
( 2023.4.1 Twitter より )
